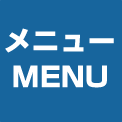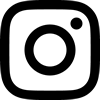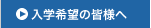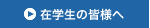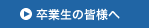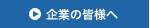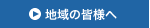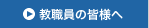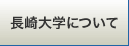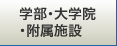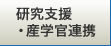ホーム > 長崎大学について > 学長メッセージ > 片峰前学長 > Journal for Peace and Nuclear Disarmamentの発行について
Journal for Peace and Nuclear Disarmamentの発行について
2017年09月26日
このたび新たに発刊します国際学術雑誌について、長崎大学長としての所感を述べさせていただきます。
この学術雑誌のタイトルは英語で、 “Journal for Peace and Nuclear Disarmament” としました。核軍縮に特化した、きわめてユニークなジャーナルで、この分野において、世界のトップジャーナルを目指したいと考えています。
ご承知のように、長崎大学は世界で唯一の被ばく医科大学を系譜として有する国立総合大学です。1945年8月9日、キャンパスと病院のまさに真上の空で、一発の原子爆弾が炸裂しました。瞬時にして、キャンパスと病院は破壊しつくされ、約900人の学生・教職員・医療従事者の命が奪われました。
その後、復興を遂げ、現在までに日本を代表する地方総合大学として発展しましたが、原子爆弾の被爆という悲しい歴史を基盤に、大学の最も重要な目標は核兵器の廃絶と世界平和の実現にあると考えています。
長崎大学医学部においては、原爆症の治療と放射線被ばくの健康影響に関する研究が最重要のテーマであり続けています。これまでに原爆の非人間性を証明する多くの科学的証拠を世界に発信してきました。この蓄積が31年前のチェルノブイリ、6年前の福島の二つの原発事故における住民の被ばく健康リスク管理への大きな貢献につながったと考えています。
オバマ前米大統領のプラハにおける「核なき世界」演説に触発され、長崎大学は2012年4月に核兵器廃絶研究センター(RECNA)を創設し、核兵器廃絶に特化した社会科学的な研究および教育を本格的に開始しました。被爆地長崎のシンクタンクとして機能するとともに、これまでに国連で「北東アジア非核兵器地帯構想」といった政策提言を行うなど、世界の核軍縮のトレンドの中で着実に存在感を発揮してきました。
今、国連において核兵器禁止条約が122カ国・地域の賛成で採択される一方、東アジアにおいては、核戦争の危機がこれまでにも増して高まっています。RECNAの役割は今後、ますます大きくなるものと考えています。
こうしたなかで、このたびRECNAが中心となって、新しい学術誌 “Journal for Peace and Nuclear Disarmament” を発刊することは、とても大きな意味があると考えています。世界各国の核軍縮に関するトップ研究者たちの研究成果を糾合することにより、核軍縮に向けた理論構築、あるいは政策立案の議論のプラットフォームとして機能し、核軍縮の進展に貢献したいと考えています。
2017年9月2日、長崎は核兵器廃絶運動のきわめて重要な理論的支柱を失いました。長崎大学元学長、土山秀夫博士です。
これは土山博士の死を報じた長崎新聞の第一面です。 ※クリックで拡大します。
※クリックで拡大します。
博士はつねづね、核兵器廃絶を成し遂げるには「情」と「理」、この二つの要素が必要であるということを説いておられました。
被爆者の核廃絶への思い、すなわち「情」、それに加えて科学的、論理的に核兵器廃絶の正当性を説く「理」、すなわちアカデミアの役割を強調されていたわけです。
この土山博士の言葉が、5年前の長崎大学RECNAの創設をもたらしたものと考えています。
土山博士の死と、今回の新しいジャーナルの発刊決定の時期が重なったことに特別な縁を感じています。新しいジャーナルの発刊を土山博士に捧げたいと思います。
2017年9月4日
長崎大学長
片峰 茂